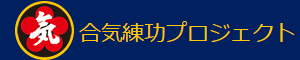Tスタイル 〜合気練功の日々〜
「マルチタスクからシングルタスクに」
木曜日の夜に行われる練功研究会(別名:バットマンの会)では、合気上げ(揚げ)を繰り返し稽古しています。松原塾長は、合気上げの重要性を何度も強調されています。合気上げができることが、合気開眼のゴールではなくスタートであるとも考えておられるようです。
毎回、色々な観点からアドバイスをしていただくのですが、なかなか上手くいきません。悩みながらある本を読んでいると、こんな事が書かれていました。
「マルチタスクは非効率」
合気上げを例に取ると、稽古の際、接触面に圧を加える・足裏を捉える・推進力を発生させる・・・等、数多くの事を同時に意識してしまいます。そうすると、意識を散らしてしまい中途半端な動きになってしまいます。これがマルチタスクの状態です。ここからシングルタスクの状態にするためには、同じ動きを何度も繰り返し行い、無意識のうちにできるようにすること、つまり自動化することが必要だということです。
うーん・・・。つまり、ポイントを押さえながら数をこなすということでしょうか。ただ、対練(相手をつけての練習)を毎日行うことは難しいですね。後は、個人練功の工夫でしょうか。
個人練功の工夫と言えば、前回のブログで書いた、練功の為に私が手に入れたアイテムとは・・・?「バランスボード」です。あえて身体を不安定な状態にすることで、相手とひとつの重心をつくり出すことを疑似体験できるのでは・・・と考えたからです。すぐに効果があがるとは考えてはいませんが、とりあえず継続して取り組んでいこうと思っています。
皆さん、シングルタスクのバットマンを目指して共にがんばりましょう!!そのうち、空も飛べるようになるかも⁈
アマゾンでマント買わなきゃ!
TAKA